2025年7月、早稲田大学、株式会社テムザック、株式会社村田製作所、SREホールディングスの4者によって、新団体「KyoHA(京都ヒューマノイドアソシエーション)」の設立が発表された。目的は、純国産の人型ロボット(ヒューマノイド)の開発と、国際競争における日本ロボット産業の巻き返しである。
一見すると、技術大国・日本の復権を告げる頼もしい動きに見える。しかし、現実には、世界の潮流との間には大きな隔たりが存在する。
KyoHA(京都ヒューマノイドアソシエーション)とは何か
設立の背景
2025年7月、早稲田大学、株式会社テムザック、株式会社村田製作所、SREホールディングス株式会社の4者により、「KyoHA(京都ヒューマノイドアソシエーション)」が発足した。この団体は、ヒューマノイドロボットの純国産開発を目的として、産学が連携し、日本のロボット産業を国際競争力のある水準に引き上げるための国家的挑戦である。
背景には、米中による急速なヒューマノイド開発の進展がある。米国ではテスラやFigure AIが、AIと制御を統合したヒューマノイドを進化させており、中国ではXiaomiやUnitree Roboticsが価格と性能の両立を武器に急伸している。対照的に、日本では部品技術は依然高水準であるにもかかわらず、システム統合力と商業展開に課題がある。
高西淳夫教授(早稲田大学)
WABOTから始まる世界的先駆者
高西教授は、世界初の本格的な人型ロボット「WABOT-1」(1973年)や、ピアノ演奏ロボット「WABOT-2」(1984年)、動歩行を実現した「WL-10RDシリーズ」(1985年)などを開発。ロボティクス分野で国際的に高く評価されている(Wikipedia)。
また、2014年のディズニー映画『ベイマックス』にも技術協力しており、研究成果の社会的活用にも積極的である。
株式会社テムザック
実用ロボット「WORKROID」の開発企業
2000年設立、京都市に本社を置くロボットメーカー。実用ロボット「WORKROID」の開発で知られる(公式サイト)。
代表取締役議長:髙本陽一氏。創業時よりロボットによる社会課題解決に取り組む。下水道点検、災害救助、農業分野などでロボットを実装。
代表取締役社長:川久保勇次氏。技術畑出身で、社会実証を主導(PR TIMES)。
株式会社村田製作所
電子部品大手、センサとアクチュエータに強み
村田製作所は、センサ・アクチュエータなど高機能電子部品の世界的サプライヤー。KyoHAではロボットの”感覚”部分を担う(公式サイト)。
執行役員:川島誠氏。センサ事業や新規事業開発に携わり、小型CPAPや疲労ストレス計なども主導(JBpress記事)。
SREホールディングス株式会社
AI×クラウドで産業DXを推進する企業
2014年設立(旧ソニー不動産)、本社は東京都港区赤坂。AIクラウド&コンサルティング(AICC)事業を主軸に、金融・医療・製造・不動産等でサービスを展開(公式サイト)。
- 2025年6月:ヘルスケア施設向けAIエージェント実証開始(プレスリリース)
- オープンハウス社に不動産AI査定APIを提供(年間1200時間削減)
- AIモニタリング技術で映像通信量を1/100に削減
CDO:泉晃氏(元IBM・BCG)、250件以上のデータ利活用支援経験を持つ。ロボティクスに知見を持つ佐々木啓文氏、新村仁氏もプロジェクトに関与。
意義と挑戦
KyoHAは、「部品の国・日本」が再び「システム全体をつくる国」となることを目指した産業横断プロジェクトである。その意義は、国産技術の集合知を結集し、海外依存から脱却した自律的技術体系を構築する点にある。
ただし、国際的にはすでに数世代先を進む米中韓のプレイヤーが存在しており、技術の深さだけでなく、開発スピード・資本規模・社会実装力の面で圧倒的な差がある。
日本の強みである精密部品と高信頼設計を基盤としつつ、どこまでシステム統合力を高め、かつ商業的に成功させられるかが鍵となる。
村田製作所とは何か:ロボットではない日本の技術の中核
村田製作所は京都府長岡京市に本社を置く、日本を代表する電子部品メーカーである。積層セラミックコンデンサやセンサー、通信モジュールなど、高性能・小型部品をグローバルに供給しており、その技術はスマートフォンや自動車、医療機器など、現代社会のあらゆる電子機器に不可欠である。
村田はこれまで、システムインテグレーターではなく、コンポーネントの供給者として国際競争に臨んできた。つまり、「全体をつくる」プレイヤーではなく、「支える部品を極限まで高性能にする」プレイヤーである。この特性は、日本の産業全体の構造にも重なる。
KyoHAにおいて村田は、センサーやアクチュエーターなど、ヒューマノイドの神経や筋肉に相当する精密部品の供給を担う。つまりKyoHAは、「日本型モジュール技術」を結集し、全体最適へと持ち上げる試みである。
世界のロボット覇権構造
ボストン・ダイナミクス=現代(Hyundai)子会社なども有名だか、やはりロボット産業は米中がトップをいく。
米国:テスラとFigure AI
米国では、テスラ社が「Tesla Optimus」という汎用人型ロボットを実用化に向けて開発中である。Figure AI社も、OpenAIやMicrosoft、NVIDIAなどから出資を受け、「GPT-4oと連携するヒューマノイド」を実演して話題を集めた(2024年)。AIとロボットを統合する垂直統合型の戦略が特徴である。
中国:小米(Xiaomi)とUnitree
中国では国家戦略としてロボティクスが推進されており、Xiaomiの「CyberOne」やUnitree Roboticsの低価格・高性能なロボットが市場を賑わせている。特にUnitreeの機体は、価格帯が10万円台からと異常に安価でありながら、二足歩行やダンス、ジャンプなど高度な運動性能を実現している。
日本の「弱さ」はなぜ生じたのか
日本のロボティクス産業は、かつて世界を先行していた。1980年代のWABOTやASIMO、HRPシリーズなどは象徴的だ。しかし、以下の3つの構造的課題が、世界との圧倒的な差を生むに至った。
- 統合不全:部品メーカーは優秀だが、「一体型製品」をつくる企業体制が希薄
- AI技術の遅れ:ハードに比してソフトウェア(特にLLMや強化学習)の遅れ
- 国策・資本投下の不足:米中のような国家主導の研究開発資金や戦略が欠如
KyoHAの限界
KyoHAは、このような状況において、「もう一度、日本がロボットの全体をつくる」ための産学連携モデルである。村田の精密部品、テムザックのフィールド実装、早稲田の研究知見が統合される点で、日本型の「職人連合」による巻き返しともいえる。
しかし、国際競争の速度とスケールの前では、まだ構想段階にあるKyoHAは遅れてスタートを切ったに過ぎない。自動車産業でトヨタが果たしたような「全体を設計し、量産する統合能力」を、誰が担うのか。その問いは、依然として残されたままである。
おわりに
KyoHAの設立は、日本の産業界がようやく“全体をつくる責任”に目を向けた大きな一歩である。村田製作所のような企業が中核を担うことは、技術的信頼性の裏づけともなるだろう。
しかし、現実はきびしい。すでに世界は「AIで動く全自動ヒューマノイド」を視野に入れており、その実証も始まっている。日本が真に追いつくためには、KyoHAのような個別連携だけではなく、国家戦略としての資本投入と人材育成、そして社会実装までを含む“エコシステム全体の再設計”が不可欠である。
この構造転換を果たせるか否かに、ロボット先進国・日本の未来がかかっている。
ただ、個人的にはとてもうれしく楽しみなニュースだ。

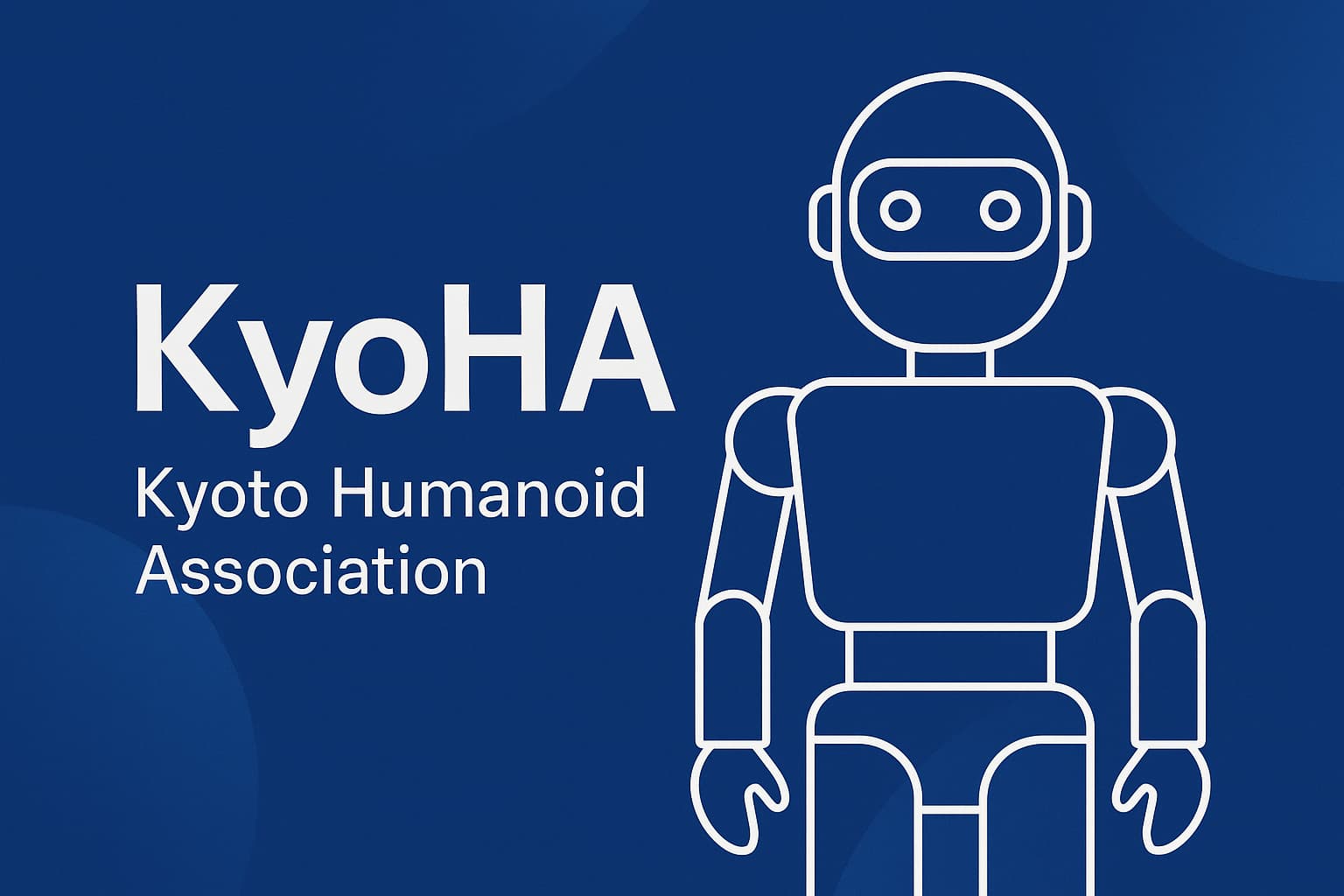


Comment