AIがソフトウェア開発を支えるようになった今、私たちが直面しているのはスピードではなく秩序の問題です。
思いついたことをAIに投げてコードを吐き出させる「Vibe-Coding(雰囲気コーディング)」は便利ですが、その場しのぎに終わりやすく、あとで必ずツケが回ってきます。
GitHubが公開した SPEC.Kit は、その無秩序をただすための「フレームワーク」です。
コードではなく仕様を出発点とする「仕様駆動型開発(Spec-Driven Development, SDD)」を可能にします。
なぜSPEC.Kitが必要なのか
Vibe-Codingの落とし穴
- 一見うまく動くコードが出ても、本来の意図とずれている
- 本番に向かない技術スタックを選んでしまう
- チームで維持するには不安定で、負債が積み上がる
「すぐ動くけど、あとで直すのに倍以上かかる」――そんな経験がある人は多いはずです。
SPEC.Kitの考え方
- 仕様が王様:コードは仕様を表現した結果にすぎない
- 仕様は実行可能:AIがその仕様をもとに実装やテストを生成できる
- 秩序ある流れ:仕様 → 計画 → タスク → 実装の順に進め、各段階で人がチェック
つまり、「設計図なしの家づくり」をやめ、「仕様書を土台にした開発」へと発想を転換させるのです。
SPEC.Kitの全体像
主な構成要素
- CLI(コマンドライン)
プロジェクト初期化や仕様作成を進めるための操作窓口 - テンプレート
仕様・計画・タスクの雛形がそろっている(マークダウン形式) - プロンプト
AIエージェント(Copilot、Claude、Geminiなど)に渡すための最適化済み指示文
プロジェクト構造(例)
| ディレクトリ/ファイル | 役割 |
|---|---|
| memory/constitution.md | プロジェクトの「憲法」。守るべきルールを記載 |
| templates/ | 仕様や計画のテンプレート群 |
| specs/ | 実際に生成された仕様ファイル |
| scripts/ | ブランチ作成などの補助スクリプト |
とくに重要なのが constitution.md。
ここに「ライブラリは優先的に使う」「セキュリティはOWASP準拠」といった原則を書いておくと、AIはそれを破れなくなります。
四段階ワークフロー:SPEC.Kitの使い方
SPEC.Kitの流れはシンプルですが、徹底されています。
1. Specify(仕様定義)
「何を、なぜ作るのか」を書きます。
実装方法はあえて書かないのがポイント。
例)
/specify
ユーザーはタスクを追加・完了・一覧できる。
受け入れ基準:E2Eテストで3操作が通ること。
非機能要件:TTI 2秒以内、XSS/CSRF回避。
2. Plan(計画)
仕様を受けて、どう実装するかを決めます。
例)
/plan
フロント:Next.js
UI:shadcn/ui
API:REST(JSON)、OpenAPI雛形を生成
DB:PostgreSQL
認証:httpOnlyセッショントークン
3. Tasks(タスク化)
計画を小さな作業に分解します。
テスト駆動を前提にするのが特徴です。
例)
/tasks
- POST /api/tasks のスキーマとテスト
- GET一覧(ページング含む)
- UIフォームのバリデーション
- E2Eシナリオ(追加→完了→一覧)
- CSRF対策と入力エスケープ
4. Implement(実装)
AIがタスクごとに実装。人間は「検証者」としてレビューします。
導入手順(クイックスタート)
前提環境:Linux/macOSまたはWSL2、Python 3.11以上、uv、Git。
新規プロジェクトの場合:
uvx --from git+https://github.com/github/spec-kit.git specify init my-app
既存ディレクトリで利用する場合:
uvx --from git+https://github.com/github/spec-kit.git specify init --here
その後、利用するAIエージェントを選び、/specify → /plan → /tasks → 実装 の流れで進めます。
Windows×GitHubCopilotで使うための全体像
必要なもの(WSL側に入れる)
| 項目 | どこに入れる | 備考 |
|---|---|---|
| WSL2(Ubuntuなど) | Windowsに有効化 | wsl --install が最短。WSL2が既定。(Microsoft Learn) |
| Python 3.11+ | WSL内 | uvで入れるのが速い。(Astral Docs) |
| uv | WSL内 | ツール実行ランチャー。uvx --from ... がポイント。(Astral Docs) |
| Git | WSL内 | 認証はGit Credential Managerも使える。(GitHub) |
| SPEC.Kit(Specify CLI) | WSL内 | uvx --from git+... specify init で初期化。(The GitHub Blog) |
| VS Code + WSL拡張 | Windows(VS Code本体) | WSL内のフォルダをVS Codeで開く。(Visual Studio Code) |
| GitHub Copilot(Chat) | VS Code拡張 | セットアップはVS Codeの公式手順どおり。(Visual Studio Code, GitHub Docs) |
セットアップ(15〜30分)
1. WSL2を有効化(Windows)
PowerShell(管理者)で:
wsl --install
再起動後、Ubuntu等の初期設定を完了。WSL2が既定です。(Microsoft Learn)
2. VS Code + WSL拡張(Windows)
- VS Code をインストール
- 拡張機能「WSL」を入れる(Remote – WSL)
- 「WSL: Open Folder」でWSL内のプロジェクトを開く
(WSL拡張は、Linux環境の開発をWindows上のVS Codeで快適にするための公式手順です。)(Visual Studio Code)
3. uv & PythonをWSL内に導入(Ubuntu想定)
WSLのターミナルで:
# uv を導入(公式インストーラ)
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
# Python 3.11+ を用意(uvはPythonも管理できる)
uv python install 3.11
uv python install --default 3.11 # python/python3を指すエイリアスに設定(実験的フラグ)
(uv公式ドキュメントの手順に準拠)(Astral Docs)
4. Git をWSL内に
Ubuntuなら sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git。
Git認証で困ったらGit Credential Manager(Linux版)も利用可(SPEC.KitのREADMEのトラブルシューティング記載)。(GitHub)
5. GitHub Copilot(VS Code)
VS CodeのCopilotセットアップを実施(サブスク契約 → 拡張導入 → サインイン)。Chat拡張も自動または併せて導入。(Visual Studio Code, GitHub Docs, Visual Studio Marketplace)
プロジェクトの作成(Copilot想定)
1. SPEC.Kitを初期化(WSL内)
uvx --from git+https://github.com/github/spec-kit.git specify init my-app --ai copilot
# 既存ディレクトリで始めるなら
uvx --from git+https://github.com/github/spec-kit.git specify init --here --ai copilot
--ai copilotを公式が明示。SPEC.KitはCopilot/Claude/Gemini対応。(GitHub)
なぜuvx?
uvの--from git+...で、GitHub上のCLIを即時実行できるからです。(Astral Docs)
2. できあがる構成(抜粋)
memory/constitution.md… プロジェクトの憲法(原則・禁止事項)templates/…spec-template.md/plan-template.md/tasks-template.mdspecs/… 実際の仕様書が入る場所
(構成はREADMEに記載)(GitHub)
よくある質問と対処
Windowsネイティブじゃだめ?
WSL2前提です(Linux/macOS、WindowsはWSL2)。(GitHub)
Copilotで本当に使える?
使えます。 公式がCopilot / Claude / Gemini対応を明記。初期化時に --ai copilot を指定できます。(The GitHub Blog, GitHub)
エージェント検出で詰まる
--ignore-agent-tools を付けてテンプレートだけ取得も可能。(GitHub)
Git認証が通らない(WSL)
Git Credential Manager(Linux版)の導入スクリプトがREADMEのTroubleshootingにあります。(GitHub)
「憲法」サンプル(抜粋)
# Principles
- Library-First(車輪の再発明をしない)
- Test-First(受入基準→テスト→実装)
- Security Baseline(OWASP ASVS L2)
# Prohibitions
- 仕様にないAPIの追加禁止
- 認証の独自実装禁止
(理念は公式ブログの説明する「仕様を真ん中に置く」流れに合致)(The GitHub Blog)
つまずきにくい運用のコツ
コストを抑える(トークン・時間)
- 1仕様=1機能に小分け
- 差分更新の思考(すべてやり直さない)
- E2Eの合格条件を最初に固定(迷いを減らす)
(「段階ごとに検証する」—公式の型と一致)(The GitHub Blog)
VS Code側のベストプラクティス
- WSL拡張は必須(補完・デバッグ等の面で推奨)(Microsoft Learn)
- CopilotセットアップはVS Codeの手順に沿う(サインイン→拡張)(Visual Studio Code, GitHub Docs)
参考:公式が示す全体フロー(確認用)
- Prerequisites(Linux/macOS、WindowsはWSL2、Copilot/Claude/Gemini、uv、Python 3.11+、Git)(GitHub)
- 初期化コマンド:
uvx --from ... specify init <PROJECT_NAME>(--ai copilot可)(The GitHub Blog, GitHub) - ワークフロー:
/specify → /plan → /tasks → 実装(エージェント横断)(The GitHub Blog)
出典
- GitHub SPEC.Kit リポジトリ(README/詳細手順/Prerequisites):WSL2・Copilot/Claude/Gemini対応、
--ai copilot、Troubleshooting等。(GitHub) - GitHub 公式ブログ:SPEC.Kitの狙いと4フェーズ、複数エージェント対応。(The GitHub Blog)
- WSL 公式(Microsoft Learn):
wsl --install、WSL2の基本、VS Codeとの接続。(Microsoft Learn) - uv 公式ドキュメント:インストール方法、
uvx --from git+...の使い方、Python導入。(Astral Docs)
これで、Windows + GitHub CopilotでSPEC.Kitを実際に使えるはずです。
競合との比較:Kiro.devとSPEC.Kit
| 項目 | GitHub SPEC.Kit | Amazon Kiro.dev |
|---|---|---|
| 位置づけ | 開発フレームワーク(CLI) | IDEに統合された一体型環境 |
| ライセンス | MIT(無料・OSS) | プロプライエタリ(有料) |
| AIエージェント | Copilot、Claude、Geminiなど複数対応 | Claude中心 |
| 強み | オープン、拡張性、既存環境に統合しやすい | 統合体験、オールインワン |
| 弱み | セットアップに摩擦あり | ベンダーロックと自由度の低さ |
SPEC.Kitは「自分で選べる自由」を、Kiro.devは「全部そろった安心感」を提供する、と言えるでしょう。
コミュニティの反応
評価されている点
- 無料で使えること
- 思考のフレームワークとして役立つこと
- コードの品質と一貫性が上がること
批判されている点
- ステップが多く「slog(骨の折れる)」と感じる
- トークンを大量に消費する
- WindowsサポートやVS Code拡張がまだ未成熟
実務ガイド:失敗しない導入計画
まずは小さな勝利を
- 小規模の新規プロジェクトで試す
- 特に複雑な機能の設計に使う
- レガシー刷新の際、仕様抽出に活用する
コスト管理の工夫
- 1仕様=1イシューに分割
- 変更点のみ差分で再実行
- 最初にE2E基準を決める
チェックリスト
- 憲法(constitution.md)を定義したか
- 各フェーズの承認者を決めたか
- OpenAPIやデザイントークンなど「機械が読める資産」を整えたか
- 運用メトリクスを仕様に戻す仕組みがあるか
結論
SPEC.Kitは、AI開発を無秩序な実験から秩序ある工学へと引き戻すフレームワークです。
「すぐ動くコード」ではなく「長く使えるコード」を手に入れるために――。
まずは小規模で導入し、憲法と仕様の運用に慣れていくこと。
それが、将来に向けた最大の投資になるでしょう。
付録:実務で使えるテンプレート
spec-template.md(要約)
# Feature: 機能名
Goal: ユーザー価値
Acceptance Criteria: E2Eで検証可能
Non-functional: 性能/セキュリティ
plan-template.md(要約)
Stack: FE/BE/DB/Infra
API: OpenAPI
Testing: Unit/Integration/E2E
Security: ASVS基準
tasks-template.md(要約)
[ ] ユニットテスト
[ ] API実装
[ ] UIバリデーション
[ ] E2Eテスト
[ ] セキュリティチェック


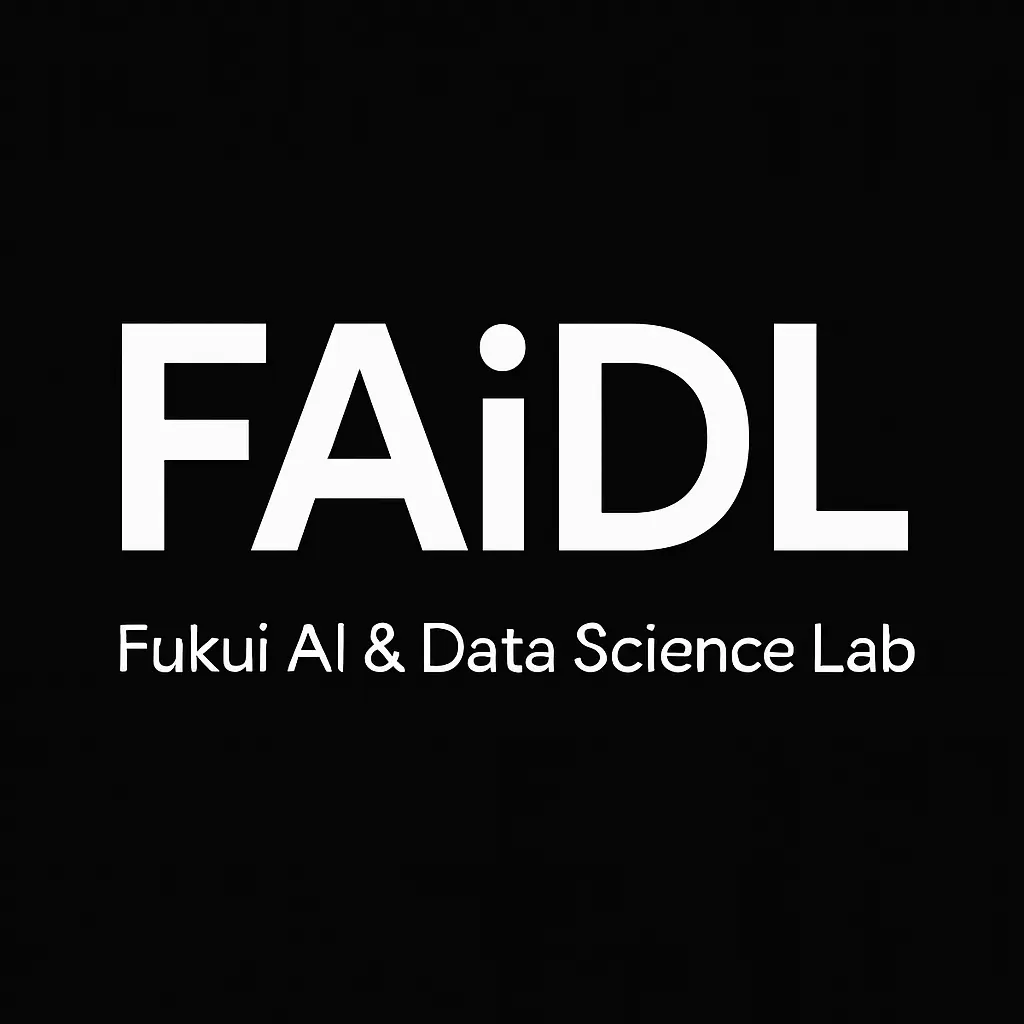
Comment