デザインの基礎である「色」。
私たち人間はいったい、いくつの色までを一度に認識・区別できるのでしょうか?
目次
一度に区別できる色の数は「おおよそ5〜10色」
これは視覚心理の分野でも研究が進められており、明確な結論はありませんが、
- 5〜10色程度が限界(通説)
- 3〜7色程度が推奨(実用上)
といった意見が多く見られます。
この根拠は、グラデーション表示や選択課題を使った心理実験に基づいており、色覚に関する被験者テストの統計値がベースとなっています。
なぜ一度にたくさんの色を識別できないのか?
以下のような要因が影響しています:
- 加齢や視力差(コントラスト感度の低下)
- 文化・経験の差(色のネーミングに慣れているか)
- 色の類似性・背景とのコントラスト
- 配色の順序・空間配置(並べ方で錯覚が起きやすい)
心理学で語られる「マジカルナンバー7±2」
1956年にハーバード大学のジョージ・ミラー教授が提唱した心理学の法則です。
人間が一度に保持できる短期記憶のチャンク(情報の単位)は7つ前後である
色もこの「認知チャンク」の一部と考えれば、一度に区別できる数は5〜9色という見方が合理的です。
マジカルナンバー7の文化的背景
- キリスト教:7日間で世界創造、7つの大罪、7大天使
- 日本:七福神、法要の周期(初七日、七七日など)
- 社会:ラッキーセブン、1週間=7日
このように、「7」という数には古代から文化的・宗教的な意味が強く結びついています。
ただし最新説は「マジカルナンバー4±1」
2001年にネルソン・コーワン教授が唱えた新しい見解です。
実際に人が一度に記憶・処理できるのは4つ程度のチャンクである
これはより厳密な統制下で行われた実験に基づいており、色や図形などを一度に判別できる数も:
- 実は3〜4色が限界
- それ以上は認知負荷が急激に増す
とされています。
Webデザインでの実用ルール(推奨配色構成)
- メインカラー:1色(ブランドや印象の軸)
- サブカラー:1〜2色(補助や階層の表現)
- アクセントカラー:1色程度(視線誘導や強調)
また、ナビゲーションなどの項目数は7以下が推奨されており、視認性・操作性の観点でも理にかなっています。
結論:色の使用数は「3〜7」がベスト
認識限界としては10色前後を区別できますが、デザイン上適切なのは3〜7色程度まで。
- 記憶に残りやすく
- 混乱が少なく
- 統一感のある配色になる
色の選択肢が多いときほど、目的を明確にし、色数をしぼることが大切です。
過剰な彩度・バリエーションは、かえって伝わらないデザインになります。
補足:色覚多様性にも配慮を
最後に忘れてはいけないのが「色覚バリアフリー」の視点です。
- 色覚異常(色弱)を持つ人でも識別可能な配色を選ぶ
- 単に色だけで区別せず、形や文字情報を併用する
- Color Oracle や ColorBrewer といったツールの活用がおすすめ
アクセシビリティを意識した配色は、すべてのユーザーに優しいデザインにつながります。

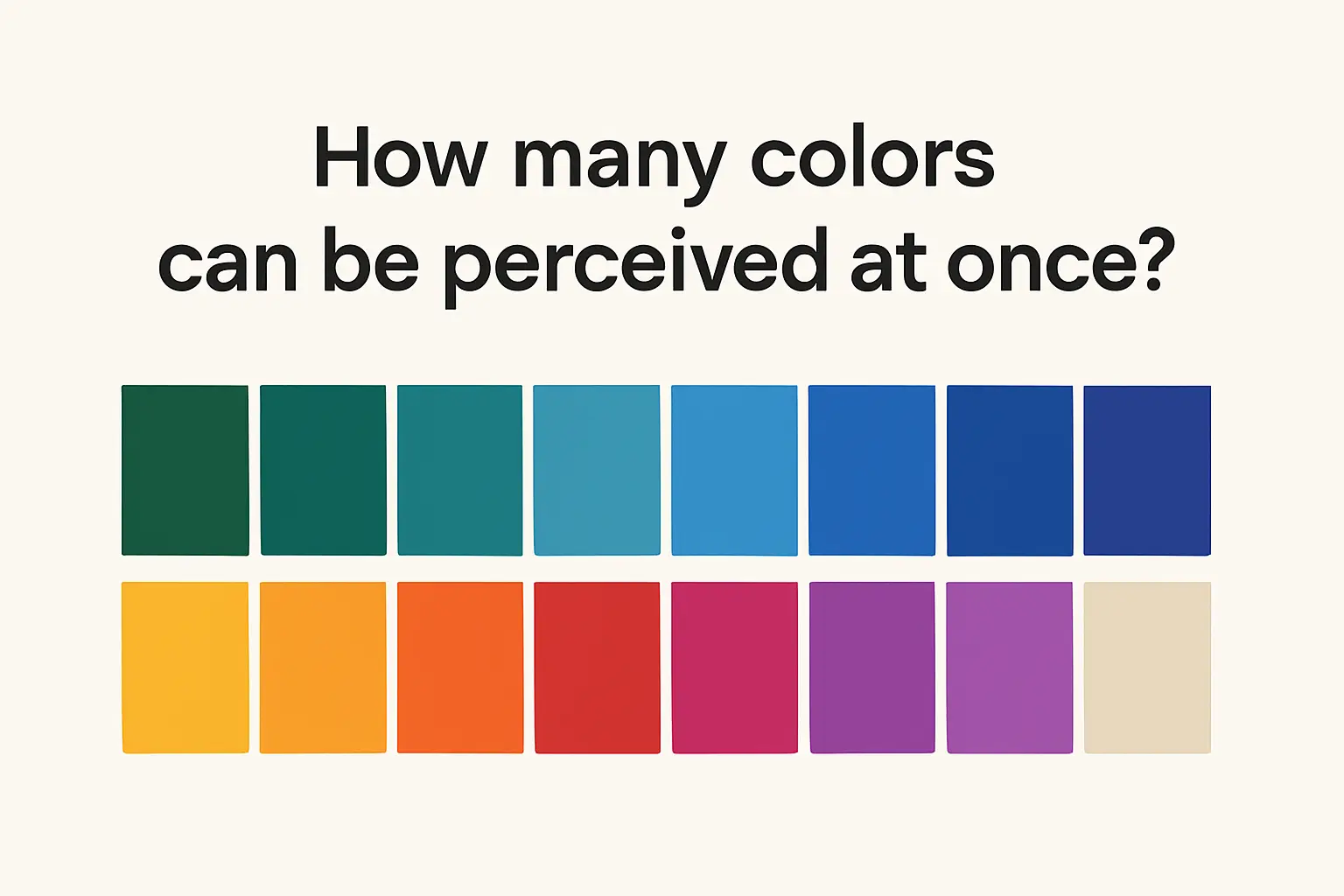

Comment